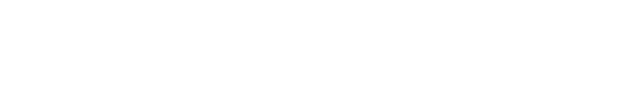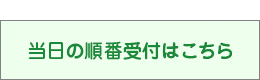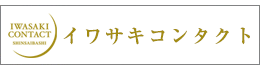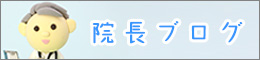加齢黄斑変性
加齢黄斑変性とは、網膜の中心部の黄班という視力を出す重要な箇所に加齢が主原因で発生して視力などの視機能が低下する疾患です。
眼球断面図(参天製薬 資料から)
加齢黄斑変性は、50歳から増え始め、日本では男性に多い疾患です。
この20年ほどで患者数は増加し、欧米では65歳以上の人の失明原因疾患の第2位で、日本における失明原因疾患では第4位となっています。
緑内障 28.6%
網膜色素変性症 14.0%
糖尿病網膜症 12.8%
白神史雄 他. 厚生労働省 総括/分担研究報告書. 2017から
【加齢黄斑変性の原因】
いろんなものが原因と考えられていて、確定的なものはありません。一番の大きく影響するとされている原因は加齢ですが、他に 喫煙、偏った食生活、紫外線、肥満 などが挙げられています。
【加齢黄斑変性でみられる症状】
発症の当初は、ものが歪んで見える変視症が出ることが多いです。
その後進行してくると、視力低下、コントラストの低下、真ん中が暗くなる中心暗点といった症状が出てきます。症状の有無や進行度合いを確認するため、時々片眼ずつでものを見るようにしましょう。
【加齢黄斑変性のタイプ】
加齢黄斑変性には大きく分けて2つのタイプがあります。
◎滲出型・・病的な新生血管ができて、網膜に浮腫や網膜剥離、出血などを生じて、初期から視力が低下することが多いです。日本人ではこのタイプが約9割です。
◎萎縮型・・黄斑の網膜がゆっくりと萎縮して徐々に視機能が低下するタイプです。欧米人 多く、日本人では約1割ほどです。今のところ、このタイプには積極的な治療法はなく、経過観察となります。
滲出型加齢黄斑変性 萎縮型加齢黄斑変性
【加齢黄斑変性の治療】
加齢黄斑変性は、発症後の自然経過で視力など視機能が確実に低下するので、診断がつき次第早々に治療を開始することが重要です。
萎縮型は、効果的な治療法がない現状ですので、食生活の改善やサプリメント接種、禁煙などをしながら定期的な経過観察を行います。
滲出型では、浮腫や網膜剥離、出血などを生じる病的な新生血管の発生や拡大を抑制するため以下のような治療を行います。
- 抗血管内皮増殖因子療法(抗VEGF療法)
新生血管の発育を促進させる 血管内皮細胞増殖因子(VEGF※) の活性を抑制する薬剤を眼球内(硝子体内)に注射して、疾患の進行を抑止します。※ (VEGF:vascular endothelial growth factor)
現在の加齢黄斑変性で、第一選択となる治療であり、当院でも6種類の薬剤(ルセンティス、アイリーア、アイリーア8mg、ベオビュ、バビースモ、ラニビズマブバイオシミラー)を採用しています。関西医科大学在職中に全ての薬剤の発売前の臨床試験から関わり、発売後も多くの症例に投与してきた経験と実績に基づき病気のタイプや活動性により使い分けています。
(図:ノバルティス社資料より引用)
- 光線力学療法(PDT:photodynamic therapy))
特殊なレーザー光を受けることで活性化する薬剤を静脈内に注射して新生血管に分布させた上で、弱いレーザーを照射して新生血管を閉塞させる治療です。加齢黄斑変性への効果は高いですが、現在は抗VEGF療法が第一選択であり、抗VEGF薬の効果が弱い患者さんに行うことが多くなっています。当院にはレーザー装置を置いていないので、適応のある方は、近隣の専門病院にご紹介しています(大阪歯科大学附属病院、関西医科大学総合医療センター、大阪公立大学附属病院など)。
(図:ノバルティス社資料より引用)
- iPS細胞 由来網膜色素上皮シート移植治療(未承認;現在臨床試験中)
iPS細胞(人工多能性幹細胞)で作った網膜色素上皮細胞を加齢黄斑変性の患者さんの眼底に移植する臨床研究が平成25年から行われています。まだ、実際の治療としての承認は得ていませんが、臨床試験では大きな副作用もなく承認に向けて現在も臨床試験が進められています。
(理化学研究所 ホームページより)
|
|